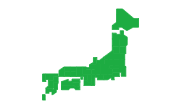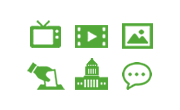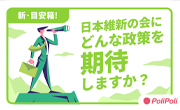Lower social insurance premiums
社会保険料を下げる改革提言
社会保険料を下げる改革提言 目次
2025年(令和7年)6月
第一章 医療・介護保険
第1 現状と課題 ~ なぜ社会保険料を下げる改革が一番大事なのか
わが国が直面する静かなる有事である少子高齢化は、政権与党の不作為も相まって、日本の社会と経済の活力と財政の基盤を毀損し続けている。日本の社会保障制度は、支える側の激減と支えられる側の膨張によって、命に係わる医療・介護の核とともに、将来の持続可能性を失っている。
危機的な状況は、年間47兆円に達し、なおも年間1兆円ずつ増え続けている国民医療費の異常な増加傾向に最も顕著に現れている。2040年には約1.7倍1にまで膨張することが見込まれている。この9割以上が社会保険料と税の負担増によって賄われており、既に50%に達しようとする国民負担率の上昇にさらなる拍車をかけている。中長期の経済低迷による賃金の停滞や物価高も加わり、現役世代の生活は悪化の一途を辿っている。
後期高齢者支援金制度に象徴されるように、これまで働く現役世代に高齢者の負担を負わせ続けた結果、現役世代に課せられる社会保険料の負担は、もはや限界に達している。
年収350万円の単身世帯では所得税は年間約7万円であるが、社会保険料は年間約50万円となっている。さらに、その同額を雇用主が負担していることから、社会保険料負担は企業による賃上げや雇用の抑制にもつながっている。
制度の信頼低下による将来不安と際限なき負担増は、若者の結婚や子育ての自信を奪い、消費や投資の意欲をも削ぎ、少子化を深刻化させるという悪循環を生み出している。
社会保障制度を持続可能にし、国民の安心で豊かな暮らしを守る鍵は、既得権政治を排した抜本改革によって国民医療費を始めとした社会保障支出の膨張傾向を断ち切ることにある。それらの改革の果実は、最終的に現役世代にとっての「社会保険料負担の軽減」という形で現れる。社会保険料を下げる改革には、今の日本が解決すべき根本的な課題が凝縮されている。わが党はこれを日本再生のセンターピン(最重点政策)と捉え、実現を目指す。
1出典:厚生労働省「医療・介護費の将来見通し」(平成30年5月)
第2 改革の方向性
-
1.
供給側:医療介護産業の生産性革命
医療費は介護費と合わせて日本のGDPの約1割を占め、経済規模で言えば自動車産業と同等である。しかし、その内実は大半が税と保険で賄われており、市場のチェック機能が働きにくい。加えて、人件費の比率が7割にも達する労働集約型の産業であるため、資源の配分や効率性の面で問題が生じやすい。
既得権を打破して岩盤の規制や仕組みに切り込むことにより、この大規模産業に対して人件費の適正化や効率的な運用モデルへの転換などの構造改革を断行する。他の産業と同様に、一定の市場原理を働かせることでサービスの質を上げながらコストを下げていく。併せて、国民皆保険制度を守るため、医療システム自体の持続可能性を高め、将来にわたって質の高い医療サービスを全ての国民に提供できる体制を確立する。
それを進める上での前提はDX(デジタル・トランスフォーメーション)である。医療産業全体の効率化を進めていくため、DXにより実態を正確に把握し、適切な対処を行うためのデータ収集が可能な環境をつくる。また、オンラインやAIによる診療の推進などにより、医療の生産性を高め、病院や医者への負担、負荷を減らすための大胆な規制改革を行う。
-
2.
需要側:保険制度を持続可能にする負担構造
現行の制度では、相対的貧困世帯など経済的余裕がなくともただ若いというだけで窓口3割負担を免れない。一方で、資産があり、生活にゆとりのある年金暮らしの高齢者の多くが窓口1割負担となっている。政府は実際の負担能力に応じた社会保険料負担のあり方、すなわち「応能負担」を推進しているが、受益と負担の不平等を解消しているとは言い難い。これを、制度を持続可能にする水準にまで深化させていく。
また、そもそも社会保険とは、より多く活用した人がより得をする「無料または割引のサービス提供」ではなく、万が一の備えとしての「保険」であるという原則に立ち返り、被保険者の受益と負担の在り方を再構築する。例えば、健康で医療サービスを使わない人は保険料負担が下がるような保険原理の適用も併せて検討していく。
社会保険料の真の負担能力を正確に把握するため、マイナンバーカードの普及率100%を早期達成し、同制度を活用して受益と負担の把握ができる状態を一日も早く実現する。現在、マイナ保険証の利用率は3割に満たず、大手銀行での預金口座の紐づけは5%以下である。
将来的には税と社会保険料の徴収や給付金などの支給業務をデジタル化によって一元管理する「デジタル歳入給付庁」を実現する。
第3 実現する果実 ~ 社会保険料をどれだけ下げるのか
後述の「第4解決策の提案」において示す改革項目を着実に実施することで、政府が自発的に取り組んでいる削減の上乗せ分として、国民医療費の総額を年間で4兆円以上削減する。これにより、年間1兆円の急速な増加傾向を止め、その後のさらなる改革へと繋げていくことで、増加傾向から現状維持へ、現状維持から減少傾向へと段階的に軌道を変えていく。
当初の4兆円以上の国民医療費の削減分については、現役世代から高齢世代への仕送りとなっている後期高齢者支援金等の削減に中心的に充てることで、現役世代一人当たり年間6万円※の社会保険料を引き下げる。また、その後も改革を進めていくことにより、この数字をさらに大きくしていく。
※国民医療費削減額の4兆円を各保険制度(協会けんぽ、組合健保、共済組合、市町村国保)における被保険者数約6,400万人で除算した金額(厳密には62,500円)であり、給与の等級等を踏まえない単純平均値となる。なお、第2号保険者は労使折半のため、労働者負担分と事業主負担分の合算となる。
第4 解決策の提案
現役世代の社会保険料の引き下げを実現するため、以下の改革の具体策について実現を図る。
政党としての政策実現の道筋は、与党と組んで国会の多数を獲り、法案成立や政府の政策に反映させる方法と、野党と組んで世論の後押しを受けて法案や政策に反映させる方法との2つがある。現在の与党過半数割れの国会状況下においては、後者の選択肢も有効であるため、選択肢としては常に持ちつつ、まずは2025年予算成立時の賛成条件として得た自民党・公明党との合意に基づく協議体での政府与党との折衝を通して、予算案、法案、診療報酬改定案等に提案を反映させていく。
なお、選挙を通して政権与党となり、自ら国会と政府を動かして実現を図っていくことが最終的な目的であることは言うまでもない。
【2026年度の実現に向けて骨太の方針に盛り込まれた項目】
-
1.
新たな地域医療構想に向けた病床削減
人口減少等により不要となると推定される、約11万床の余剰病床(一般病床・療養病床・精神病床)について、地域の実情を踏まえ、次の地域医療構想までに削減を図る。当該削減が実現した場合、一定の合理性のある試算に基づけば、約1兆円の医療費削減効果が期待できる。その上で、感染症等に対応する病床は確実に確保することなどを考慮した上で、削減病床の精査を行う。
-
2.
医療DXを通じた効率的で質の高い医療の実現
現時点の電子カルテ普及率が約50%であることを踏まえ、普及率100%を達成するために5年以内の電子カルテを含む医療機関の電子化を実現する。また、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子カルテを通じた医療情報の社会保険診療報酬支払基金に対する電磁的提供を実現する。
-
3.
OTC類似薬の保険給付のあり方の見直し
OTC類似薬の保険適用除外を含む保険給付のあり方の見直しについては、医療の質やアクセスの確保、患者の利便性に配慮しつつ、令和7年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、令和8年度から実行する。その際、こどもや慢性疾患を抱える方、低所得の方の患者負担等に配慮するとともに、個別品目に関する対応についても、これまでの湿布薬等に関する対応を踏まえて、適正使用の取組を検討する。あわせて、セルフメディケーション推進の観点から、スイッチOTC化に係る政府目標の達成に向けた取組を着実に進めるとともに、夏以降、制度面での必要な対応を含めて更なる実効的な方策を検討する。
-
4.
地域フォーミュラリの全国展開
有効性や安全性に加えて、経済性を踏まえて作成される「地域フォーミュラリ」(「医薬品のリスト・使用指針」)の導入について、その普及に向けて、後発医薬品のさらなる使用促進や患者の自己負担抑制等の観点から普及推進策を検討し、各地域における地域フォーミュラリの策定を推進する。
-
5.
金融所得の窓口負担への反映(現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底)
医療・介護保険において現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しの観点から、税制における確定申告の有無により医療費の窓口負担及び高額療養費の自己負担限度額を定める所得区分の判定が変わる社会保険の応能負担における不公平な取扱いを是正する必要がある。マイナンバーの記載や情報提出のオンライン化の課題等に留意しつつ、どのように金融所得の情報を反映させるかを含め、具体的な制度設計を進める。年齢に関わらず負担能力に応じた負担を目指す観点から、現役世代から後期高齢者への支援金負担の軽減に配慮する。
【今後の協議を通じて実現を図っていく項目】
-
1.
公的保険と民間保険のあり方の検討
コアな医療を公的保険で確実に補償しつつ、民間保険の活用方法を含めた医療保険システムのあり方を検討することで、医療の高度化等による薬剤費の高額化と保険料負担の抑制を両立させ、患者の高度医療へのアクセスを守る。この改革により期待できる医療費削減効果は、年間1兆円~2兆円程度と試算される。
-
2.
医療の費用対効果確認の徹底
予算的な影響の大きな医薬品等について、保険適用に関連して実施する費用対効果評価において費用対効果が悪いとされた医薬品等を診療に用いる場合、保険適用除外を中心とした評価のあり方を整理することで、費用対効果の優れた医薬品等の開発を促進する。
-
3.
低価値医療の保険適用の見直し
「ウイルス」感染である風邪に対して「細菌」に効果を有する抗菌薬を処方するなど、健康上の利益に関するエビデンスに乏しい「低価値医療」の保険適用を除外することで、不要な医療費の抑制と医療資源の効率化を図る。この改革により期待できる医療費削減効果は、最大2,400億円程度と試算される。
-
4.
真の応能負担の実現(窓口負担に関する世代間公平性の確保)
全世代型社会保障に向けて、高齢者と現役世代の「給付と負担」の公平性を確保するため、低所得者等へのセーフティネットを確保しつつ、高齢者の医療費の窓口負担を現行の「9割引」から原則「7割引」に見直し、現役世代と同じ負担割合とすることで、年齢に関係なく真に公平な負担のあり方を設計する。
-
5.
インフレ下における医療提供体制のあり方を踏まえた改革
インフレ下において医療給付費の伸びを名目GDPの成長率の範囲内にとどめるため、機械的な計算により自動的に抑制される仕組みの導入を検討する。
-
6.
中央社会保険医療協議会のあり方の見直し
中央社会保険医療協議会の構成員に、医薬品や医療機器メーカーといった産業側の委員を加えることを検討する。超高齢社会における我が国の医療を支える上で大きな役割を果たす看護師の視点も加える。また、社会保険料納付者の意見を代表する組織や専門家や超党派の政治家等を加えることも検討し、負担側の意見が十分に反映される仕組みにする。
-
7.
終末期医療にかかる新たな制度化
自分自身が意思表示できない状態になったときに備えて、自らが受ける医療・介護に関する価値観・選好を明確化する行為を制度化する。具体的には、リビングウィル(生前の意思表示)を全国医療情報プラットフォームに組み込むとともに、人生会議の法制化(尊厳死法の制定)を進める等、超高齢社会における終末医療の望ましいあり方を構築する。
-
8.
病院の電子カルテ等のシステムの標準化の加速化
医療介護産業のデジタル化のセンターピンとして、5年以内の電子カルテの普及率100%を達成するとともに、医療情報の電磁的提供を実現する。その際、電子カルテに関する標準化システムは、真に実効的なものとせねばならない。また、下記のマイナポータル期間連携APIを積極的に活用する等、パーソナル・ヘルス・レコード(PHR)の仕組みを整備し、1国民1カルテ体制を構築することで、医療の効率性と質の向上を図る。
-
9.
人材紹介手数料の負担軽減、ハローワークの利便性改善
医療・介護分野において活用が進む職業紹介事業において、医療経営の足枷となっている高額な紹介手数料の負担軽減やハローワークの利便性の改善を通じて、当該分野における人手不足を解消し、持続的な人材確保につなげる。
-
10.
マイナポータル期間連携API等を通じたデジタル予防医療の推進
マイナポータル期間連携APIは、わが国のパーソナル・ヘルス・レコード(PHR)として活用できる可能性を有している。したがって、マイナポータル期間連携APIを最大限活用し、自身の医療保険情報をマイナポータルサービス上で安全かつスピーディに取得できる環境を整備する。加えて、マイナポータル期間連携APIで取得できる情報を増加し、連続使用期間を延長し、アプリ等を活用することにより、自動的に使用できる情報の対象が拡大することで、予見可能性が高まることに鑑み、予防医療を推進する。
-
11.
プログラム医療機器の普及に係る市場環境の整備促進
治療用アプリを一元的に入手できる共通プラットフォームの構築に加え、費用対効果の観点から成長産業としての期待が高いプログラム医療機器を振興することで、重症化の抑制と医療費の適正化につなげる。
-
12.
介護テクノロジーとノーリフトケアの推進等を通じた介護現場の負担軽減
介護従事者の腰痛等の身体的負担を減少させ、離職率を低下させ、人材不足を防止する観点から、ノーリフトケアを導入した施設への介護報酬面での評価や、介護施設における「ノーリフトポリシー」の策定の法制化など、実効性のある対応を推進する。
-
13.
後発医薬品へのアクセス向上、バイオシミラーの使用促進
一定以上の後発医薬品が普及している現在、後発医薬品へのアクセス向上に関する意思決定権は、薬局又は医療機関ではなく、患者にあることに鑑み、後発医薬品に係るインセンティブを医療提供側から患者側へと移行するため、医療機関及び薬局へのインセンティブを廃止するとともに、後発品のある先発医薬品の選定療養を拡大する。また、高額なバイオ医薬品について、バイオ後続品(バイオシミラー)の使用を促進するため、医療提供側のインセンティブは維持したまま、上記の選定療養の考え方をバイオシミラーにも適用するなど、患者側へのインセンティブを導入する。この改革により期待できる医療費削減効果は、年間1兆円程度と試算される。
-
14.
健康寿命の延伸に資する歯科検診の普及
歯の健康が全身の健康に影響を与えることを踏まえ、全世代を対象とした定期的な歯科検診の促進や、虫歯予防に効果があるとされる水道水のフッ素濃度を調整する取り組みを推進することで、口腔を起点とした健康の維持・増進を図る。
-
15.
多剤・重複投薬(ポリファーマシー)の防止による高齢者の安全性確保
高齢者では6種類以上の投薬で有害事象の発生が有意に増加するとの調査があることを踏まえ、高齢者の安全性確保の観点から、多剤・重複投与の防止策を講じる。
-
16.
保険者機能の強化
保険者が真にその役割を果たすための能力を十分に発揮できるよう、保険者の自立性と主体性を高めるための仕組みを整備し、被保険者のためのサービスの質と費用抑制の両立を図る。
-
17.
オンライン診療の普及促進
対面診療と比べて医療費の抑制が期待できるオンライン診療の普及面で最大の阻害要因となっている診療報酬点数の低さを是正するため、初診料等について対面診療と同等の点数とするなど、オンライン診療に係るインセンティブを導入する。この改革により期待できる医療費削減効果は、長期的に数千億円規模と試算される。
-
18.
感冒様症状の検査及び予防接種に関するアクセス向上
季節性インフルエンザ及びCOVID-19等に関する迅速診断、医薬品の購入及びワクチン接種について、薬局等の医療機関外での実施を可能とすることで、国民の感冒様症状の検査・診断に対するアクセス向上を図る。この改革により期待できる医療費削減効果は、年間3,000億円程度と試算される。
-
19.
特定健診に関する効果が望まれる年齢層への集中投資
既に医療機関で受療中であることが多い65歳以上の高齢者は、特定健診による行動変容が期待しにくいことから、特定健診の対象年齢を65歳未満とし、より効果的な世代に医療資源の投資を集中させる。この改革により期待できる医療費削減効果は、年間100億円程度と試算される。
-
20.
複雑化した調剤報酬体系の簡素化
医薬分業の進展に伴い、調剤医療費のうち薬剤料等を除いた技術料部分の伸びが増大していることに鑑み、改定の都度新たな政策誘導的加算が増え続けている調剤報酬体系を抜本的に見直し、医療業務の効率化と医療費の膨張の抑制を図る。
-
21.
医療機関の外来診療における診療報酬体系のあり方の改革
医療機関における外来診療の支払い制度について、現在の出来高払い方式に加え、包括支払い方式を含む他の方式を精査し、導入を図ることで、医療機関に対して医療資源の非効率な使用や支出の抑制を促し、より低コストで効率的な医療機関経営につなげる。
第二章 年金保険
第1 現状と課題
わが国の公的年金制度は、少子高齢化が加速する中、将来世代に対する持続可能性と、現役世代・高齢者の生活保障機能との両立が求められている。しかしながら、政府与党はこの根本的な課題に向き合うことなく、問題の先送りを繰り返してきた。先の国会で成立した「国民年金法等の一部を改正する法律」(以下、「国民年金改正法」)もまた、構造的な課題の解決には程遠い小手先の改正にとどまっており、制度の持続可能性と公平性を大きく損なうものである。
これまでの年金制度改革は、2004年の「100年安心」を掲げた制度改正において、マクロ経済スライドの導入や保険料の上限固定、給付の抑制などが打ち出された。しかし、名目下限措置の存在などにより給付調整は実質的に機能せず、2024年財政検証でも制度の長期的な安定性にはなお懸念が残されている。特に基礎年金の給付水準の著しい低下は、将来的に生活保護受給の増加や老後貧困の深刻化を招き、社会の分断を助長しかねない。
また、これまで議論の焦点であった第3号被保険者制度の見直しや、年金支給開始年齢の引き上げといった抜本改革については、政府は検討すら回避してきた。今回の法案でもこれらの議論は棚上げされたままであり、将来世代への負担転嫁と不公平の固定化を容認する姿勢が明確に表れている。
一方、わが党は、これまで一貫して、世代間・世代内の公平性を確保しつつ、持続可能な年金制度を構築するための抜本的改革を訴えてきた。年金制度改革は国民生活に直結する最重要課題の一つである。日本維新の会は、政府与党が抱える限界を厳しく指摘するとともに、現実的かつ公平な制度改革を提言するものである。
第2 政府の年金財政検証の問題点
今般成立した国民年金改正法は、2024年7月に公表された年金財政検証の結果に基づいて設計されているが、その財政検証自体に多くの問題が内在している。将来見通しの前提、給付水準の試算手法、制度持続性の評価指標など、検証の信頼性と政策形成機能に深刻な疑義がある。
-
1.
非現実的な経済前提とスプレッドの過大設定
政府の財政検証は、将来の実質成長率、労働参加率、物価・賃金上昇率などを基に年金財政の健全性を試算しているが、その多くは現実から乖離した楽観的な前提に依存している。
特に注目すべきは、運用利回りと賃金上昇率の差である「スプレッド」の過大設定である。2024年財政検証の基本シナリオである「過去30年投影ケース」ではスプレッドが1.7とされており、これは2019年検証時の最も好調なケースの1.4を大きく上回っている。この非現実的なスプレッドが、年金財政の見かけ上の好転に大きく寄与している。
仮にこのスプレッドが成立したとしても、金利収入が税収を上回ることになり、年金制度は維持できても国家財政が破綻するという「年金栄えて国滅ぶ」構造を助長する懸念がある。さらに、同じ政府内で厚労省と内閣府が全く異なる経済想定を掲げている点も整合性を欠いており、制度設計の正当性に重大な疑義を生じさせている。 -
2.
外国人労働者と出生率の想定の楽観性
財政検証では、少子化が進行する中で出生率が将来的に回復するという前提(1.15→1.36)という非現実的な想定に立脚している。
加えて、現役労働者としての外国人の割合が2050年に10%に達するとの想定が置かれている。外国人労働者の年金加入率は依然低く、賃金水準も日本人より低い傾向があるため、年金財政への貢献を日本人と同等に見積もることには無理がある。
政府は2066年に外国人が人口の1割を占めると想定し、生産年齢人口の支え手として位置づけているが、そのような構図が国民的合意に基づいているとは言い難く、移民政策と年金財政の一体的議論が欠如している点も問題である。 -
3.
所得代替率偏重による評価軸の限界
政府は「所得代替率50%の維持」を制度設計の目標として掲げているが、その前提となるモデル世帯(40年就労の夫と専業主婦の世帯)は現実から乖離しており、現代の多様な家族形態や就労状況を反映していない。国際標準に倣って個人単位での所得代替率を比較すると、OECDのデータで日本は38.8%となり、先進国で最低水準になっている。
さらに、代替率維持が困難な場合には「調整措置」で対応するとされており、数値目標が空文化している。政策評価の軸として、現実の高齢者の所得や生活水準を適切に把握する必要がある。 -
4.
マクロ経済スライドの機能不全と長期化
マクロ経済スライドは、年金給付の伸びを現役世代の負担能力に応じて抑制する仕組みであるが、名目下限措置の影響により、実際の給付調整はほとんど行われていない。過去20年で実際にスライドが機能したのは数回にすぎず、制度は骨抜き状態にある。
特に基礎年金では、スライド調整が2057年まで継続される見通しであり、その間に給付水準が最大で3割低下するとされる。これは最も脆弱な高齢者層に過度な影響を与えるものであり、制度設計の根幹に関わる問題である。 -
5.
未納率・納付率の実態を覆い隠す評価手法
財政検証では国民年金の納付率の改善が強調されているが、これは免除・猶予者を除いた数値であり、実質的な納付率は依然として5割を下回っている。特に第1号被保険者層の未納付問題は深刻であり、この層の制度参加が不十分なままでは、制度の持続可能性は確保できない。
減免を受けた場合を含め、未納付者は将来、年金額が半分になり、低年金者になる(全額免除を受けた場合、基礎年金は満額年金半分)。将来の高齢者は、年金では到底生活できない。
第3 国民年金改正法の問題点
2025年度の通常国会で成立した国民年金法は、非現実的な財政検証の前提に依拠し、現役世代に過度な負担を負わせたまま、既に低い給付水準の引き下げを厚生年金基金からの流用と公費投入で対処療法的に止めることで、現行制度を持続可能に見せかけているだけである。真の問題と向き合うことから逃げ、小手先の対策を打ち出しているに過ぎず、国民の将来不安が解消されることはない。制度の抜本改革を先送りし続けることは、現役世代と将来世代の信頼を損ない、ひいては高齢者の生活すらも守れなくなる。
-
1.
最低生活を保障できない給付水準の更なる引き下げ
基礎年金の最大の問題は、その給付額が40年間保険料を納めた満額でも月額69,308円であり、老後の最低生活保障として機能していないことにある。日本の年金支給額は先進国の中で最低水準である。生活保護の扶助額(生活扶助7-8万円 + 住宅扶助4-5.5万円 + 医療費免除)との逆転現象も起こり始めている。
そのような中、本法律はその低すぎる給付水準をマクロ経済スライドの調整によってさらに引き下げていくことが前提となっている。示されている施策はその痛みを一時的に和らげる程度の弥縫策である。現行制度の骨格を維持して継続する限り、就職氷河期世代をはじめとして、収入が少ない層は将来十分な年金を受け取れなくなる。
これに対し、厚生年金の積立金を流用して基礎年金を底上げする策が検討されているが、基礎年金は国庫が半分を負担する仕組みであるため、厚生年金の積立金を充てれば、それに見合う額の税金投入として、数年後には1-2兆円程度の公費投入が必要になる。給付と負担にかかる公平性と将来的な財源の面で妥当な策とはいえない。 -
2.
受益の負担の不公平性の放置
本法律は、現役世代への負担が過度に偏重している現行の賦課方式の構造的問題を解消するどころか、むしろ制度への不信と不公平感を深める内容となっている。現役世代は保険料を負担し続けながらも将来のリターンが年々低下しており、「払損」への懸念が拡大しているにもかかわらず、本法律はその不安に正面から応えていない。
さらに、未納率の高い第1号被保険者層への対策を怠ったまま、被用者保険の適用拡大を掲げても、納付率の向上にはつながらず、制度の持続性は危ういままである。
加えて、共働き世帯や単身者に比して保険料負担のない第3号被保険者に同等の基礎年金を給付し続ける不公平な構造を温存し、女性の就労意欲や労働参加にも悪影響を及ぼしている。
さらに、マクロ経済スライドの継続や遺族年金の有期化といった措置は、所得再分配機能を後退させ、低所得層や非正規雇用者を中心に制度の福祉的役割を形骸化させている。
第4 解決策の提案
日本維新の会は、国民の抱える将来の生活不安を払しょくするため、老後の最低生活を保障できる安心で公平かつ持続可能な年金制度の構築を目指す。そのために、今こそ、現行の年金制度が抱える構造的問題に正面から向き合い、抜本改革を断行する必要性を強く訴える。
-
1.
「社会保障国民会議(仮称)」の設置
近年、英国では政局に囚われない超党派の専門委員会を設けて年金改革の議論を進め、二階建ての公的年金を一階建てに変え、比例報酬分は私的年金を活用するという抜本改革が行われた。わが国の年金制度が抱える問題は英国以上に深刻であり、慣行軌道上の議論の枠内を出ることができない政府与党のみの枠組みや、通常国会の一法案の数日の審議での扱いで対処できるものではない。
抜本改革の遂行にあたっては、国民のための社会保障制度の議論は政局にしないとの合意の下、政府・与野党の枠組みを超え、制度の信頼性と合意形成を確保するための新たな仕組みが必要である。日本維新の会は、総理大臣の主催による「社会保障国民会議(仮称)」の設置を提案する。この会議は、人口・労働力・財政といった現実的な前提に基づき、今後の社会保障制度(年金・医療・介護)全体の構造改革について横断的な議論を行う場とする。与野党を超えた国会議員とともに民間の専門家等が参加し、遅くとも2025年中に改革方針を取りまとめ、次期通常国会で必要な立法措置を講ずべきでる。 -
2.
「最低保障年金」の構築
本法律での改革も含め、現行制度が前提とする最低生活保障機能を失った基礎年金を国民年金と厚生年金の両方の被保険者が受け取るという複雑かつ国民にとって意義の不明な二階建て制度を改め、基礎年金に老後の生活を安心して支えることができる十分な給付額を確保した「最低保障年金」を構築する。
その上で、英国のような加算分の「報酬比例年金」をその上に乗せた一階建ての制度を考えるなど、iDeCoやNISAが拡充される中、賦課方式で強制加入となる厚生年金の是非が問われていることを踏まえ、基礎年金に加えて厚生年金の存続・あり方も含めた年金制度を抜本的に改革する。
その際、上記の社会保障国民会議(仮称)において、基礎年金について保険料による拠出を廃止して税方式に移行する方法や、現役世代が支払った保険料を自分たちの将来の年金給付のために積み立てておき、老後にその積立金から給付を受ける積立方式に移行することを含めた制度設計を行うべきである。 -
3.
「就業促進型制度」への転換による被保険者の拡大
年金制度を持続可能にし、将来的な年金給付を最低生活が保障できる水準まで増やすための鍵は、社会全体で女性や高齢者の働きやすい社会環境を作るとともに、年金制度として全ての国民にとって働くことにインセンティブを与える制度設計にすることにより、被保険者の裾野をいかに拡大できるかにかかっている。年金制度はそうした就業促進型の制度に作り替えていくべきである。特に、次の2つの改革が重要である。
-
(1)
「現役世代」の再定義による年金受給期間の調整
年金制度の持続可能性を確保するには、現役世代(生産年齢人口)の定義を見直し、シニア世代も含めた就労人口の拡大が不可欠である。高齢者の能力や意欲を生かせるよう、雇用継続支援や就労環境の整備、柔軟な働き方の推進を一体的に進める必要がある。
そもそも、日本が世界一の長寿社会を迎える中で、年金制度の持続可能性を確保するには、マクロ経済スライドによる機械的な給付水準の引き下げでは限界がある。長寿化に伴って延びる年金の受給期間を、現役で働く人々を増やすことにより支給開始年齢を引き上げて中立化することで、最低生活を可能とする水準まで給付額を増やす方が本来の年金の趣旨に適っている。現在、日本の基礎年金の所得代替率は38.8%と先進国中で最低水準にあり、欧州諸国では支給開始年齢を67歳以上に引き上げ、所得代替率を高く維持している。例えばイタリアでは支給開始年齢が71歳で、所得代替率は87.2%である。老後の安心な暮らしを支える制度の構築を最優先とするなら、給付額をさらに減らすことで制度を形だけ持続させる現在の政府方針は再考すべきである。
-
(2)
第3号被保険者制度の段階的見直し
特に第3号被保険者制度は、保険料負担のない被扶養配偶者に年金給付を保障する制度であり、他の納付者との間に著しい不公平を生じさせている。専業主婦であれば、富裕世帯であっても保険料負担を求められず、その分は他の納付者(生活に必ずしも余裕のない共働き世帯、シングルマザーなど)で負担している。また、制度は就業抑制効果を生み、特に女性の労働市場への参加を阻害してきた。
まずは世帯年収3,000万円以上の第3号被保険者についてこの制度の適用除外とし、その後、段階的に廃止に向かうことで、全ての年金受給権は「保険料拠出実績に基づく仕組み」に一本化すべきである。なお、本見直しにあたっては、十分な負担能力のない世帯には保険料免除や納付猶予の仕組みを設け、就労困難者への適切な配慮も講じる。
-
-
4.
「デジタル歳入給付庁」の設置とマイナンバーによる税と社会保険料の一元管理
現行制度下では、複数機関が関与し手続きが煩雑で、徴収漏れや給付の不公平が生じている。また、国民一人一人が受益と負担を正確に理解することができず、あらゆる種別や所得階層から年金を含む社会保障制度について不満の声が上がっている。
国民が年金制度を自分事として理解し、信頼できるよう、年金財政の透明性向上と広報機能の抜本強化が不可欠である。すべての加入者が「納めた保険料がどのように将来給付に結びつくのか」を可視化することで、制度全体への参加意欲を高める環境を整備する。
日本維新の会は、税と社会保険料の徴収、年金や各種給付の支給を一元的に担う「デジタル歳入給付庁」の設置のための法案を提出している。マイナンバーと公金受取口座を基盤に、個人の所得・資産・負担・受益情報を統合・可視化し、AIを活用して最適な徴収・給付を行う。これにより、保険料納付状況に応じた年金の精緻な管理や、公平で迅速な給付が可能になる。基礎年金の水準向上や無年金対策にもつながるこの構想は、年金の信頼回復と持続可能な制度設計の中核を担うものである。
以上
別添資料
参議院選挙マニフェストへの反映項目
■医療・介護保険
- 日本維新の会の掲げる「社会保険料を下げる改革プラン」に則り、国民医療費の総額を、年間4兆円以上削減し、後期高齢者支援金等の圧縮により、現役世代一人当たりの社会保険料を年間6万円引き下げます。現役世代に負担を負わせ毎年1兆円ずつ膨張し続けている現行の国民医療費を抜本的に軌道修正します。
- 全世代型社会保障の理念の下、高齢者と現役世代の「給付と負担」の公平性を確保するため、低所得者等へのセーフティネットは確保しながら、総所得ベースの応能負担を制度が持続可能な水準まで深化させます。高齢者の医療費窓口負担は現行の「9割引」から原則「7割引」に見直し、現役世代と同じ負担割合とすることで、現役世代の社会保険料負担の軽減を図ります。あわせて、こども医療費の無償化にも取り組みます。
- 医療費窓口負担及び高額療養費負担限度額の所得区分判定の公平性を向上させます。特に、金融所得を含めた総合的な所得把握に基づく負担区分の設定を検討し、応能負担の徹底を図ります。
- 医療介護産業について、病院や業界団体など供給側ではなく、社会保険料納付者や患者など需要者側の視点で改革し、既得権を打破した市場原理の導入や合理化により、革命的な生産性向上を実現します。
- OTC類似薬の保険適用除外を始め、費用対効果に基づく医療行為や薬剤の保険適用除外を進め、限られた医療財源を重症患者や高額・革新的な医療治療に重点的に振り向ける制度改革を推進します。
- 診療報酬体系の再構築、後発医薬品の使用原則化、保険適用薬品の適正化、医療分業制度の見直し、職種間の役割分担の見直し・タスクシフト、地域フォーミュラリの導入などを進め、医療費削減に取り組みます。
- 無価値医療(低価値医療)の保険適用除外を進めます。健康上の利益に関するエビデンスが乏しい医療サービスを特定し、保険適用から除外することで医療資源の効率的活用を図ります。
- レセプトチェックのルール統一を行い、国民皆保険制度の元でAIやビッグデータを活用することで、医療費の適正化と医療の質の向上を同時に実現します。
- 医療現場と患者の負担軽減や感染症対策のため、オンライン診療・オンライン服薬指導については診療報酬体系や利用要件のさらなる見直しを進め、安全性を確保したうえで積極的に推進し、国民にとって使いやすいものにしていきます。オンライン診療の普及を阻害している診療報酬点数の低さを改善し、初診料等について対面診療と同等の点数とすること等により、医療機関の導入インセンティブを高める方策を検討します。
- 電子カルテ普及率100%を達成します。また、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子カルテを通じた医療情報の社会保険診療報酬支払基金に対する電磁的提供を実現します。
- 人口減少等により不要となる約11万床について、不可逆的な措置を講じつつ次の地域医療構想までに削減することで、1兆円以上の医療費を削減します。一方で、感染症等に対応する病床は確保します。
- 中央社会保険医療協議会の構成員への医薬品・医療機器メーカーの追加を検討します。ドラッグラグやドラッグロスの解消を図ると同時に、超高齢社会における我が国の医療を支える上で大きな役割を果たす看護師の視点を加えます。また、企業届出価格承認制度の導入等により薬価算定制度を見直し、医薬品の価値に基づく価格設定を可能とすること等による創薬支援強化を検討します。
- 介護現場で働くすべての方の待遇・職場環境改善を行い、また、介護・福祉の現場で活用できるロボット開発・テクノロジー導入を支援し、介護人材の負担の軽減と職場への定着(離職防止)と介護の成長産業化を図ります。
■年金保険
- 社会保障制度の抜本改革に向け、政局化を避けて年金・医療・介護の構造改革を横断的に議論する枠組みとして、与野党議員と専門家が参加し、総理大臣が主催する「社会保障国民会議(仮称)」を設置します。
- 女性や高齢者が働きやすい社会環境と働くことにメリットの多い制度設計により、保険加入者を広く増やします。受給期間調整や第3号被保険者制度の見直し等により、社会保障制度を「就業促進型」へ転換します。
- 最低生活保障機能を失った基礎年金を国民年金と厚生年金の両方の被保険者が受け取る二階建て制度を改め、老後の生活を安心して支えることができる十分な給付額を確保した「最低保障年金」を構築します。
- 社会保険料を始めとする現役世代に偏った過度な負担を徹底的に見直し、老後のセーフティーネット(年金)は積立方式あるいは税方式へと抜本的に改革するなど、世代間に不公平のない制度の構築を目指します。
- 現行の公的年金を継続する場合は賦課方式から積立方式に移行し、原則として同一世代の勘定区分内で一生涯を通じた受益と負担をバランスさせることで、払い損がなく世代間で公平な仕組みを構築します。
- 世界一の長寿国である日本において、平均的な健康寿命が延伸している状況に鑑み、現役世代、すなわち、生産年齢人口の定義を見直すことで、社会保障制度を持続可能にするとともに、社会の活力を取り戻します。
自由民主党、公明党、日本維新の会
合意
自由民主党、公明党、日本維新の会は、以下の通り合意する。

自由民主党、公明党、日本維新の会合意
-
I
教育無償化
全ての若い世代に対して多様で質の高い教育を実現するとともに、経済的事情による教育格差を是正し、子育て世帯への支援を強化する観点から、論点の十分な検討を行い、以下の改革を実現する。
-
①
いわゆる高校無償化
- ・「骨太方針2025」の策定までに大枠を示した上で、令和8年度予算編成過程において成案を得て、実現する。
- ・令和8年度から、収入要件を撤廃し、私立加算額を45.7万円に引き上げる。低中所得層への高校生等奨学給付金の拡充や公立高校などへの支援の拡充を行う。
- ・先行措置として、令和7年度分について、全世帯を対象とする支援金(11.88万円)の支給について収入要件を事実上撤廃する。高校生等奨学給付金や公立の専門高校の施設整備に対する支援の拡充を行う。
-
②
いわゆる給食無償化
- ・まずは小学校を念頭に、地方の実情等を踏まえ、令和8年度に実現する。
- ・その上で、中学校への拡大についても、できる限り速やかに実現する。
-
③
0~2歳を含む幼児教育・保育の支援
- ・更なる負担軽減・支援の拡充について、地方の実情等を踏まえ、令和8年度から実施する。
-
④
高等教育の支援
- ・更なる負担軽減・支援の拡充について、十分な検討を行い、成案を得ていく。
-
-
II
現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減
社会保障改革による国民負担の軽減を実現するため、主要な政策決定が可能なレベルの代表者によって構成される3党の協議体を設置する。
以下の点を含む、現役世代の増加する保険料負担を含む国民負担を軽減するための具体策について、令和7年末までの予算編成過程(診療報酬改定を含む)で論点の十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、令和8年度から実行に移す。- ・OTC類似薬の保険給付のあり方の見直し
- ・現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底
- ・医療DXを通じた効率的で質の高い医療の実現
- ・医療介護産業の成長産業化
上記の検討に当たっては、
- ・政府与党として、令和5年12月22日に「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」等を決定し、2023年度から2028年度にかけて、歳出改革等によって実質的な社会保険負担軽減の効果を1.0兆円程度生じさせるとされていること
- ・公明党として、令和6年9月20日に「公明党2040ビジョン(中間とりまとめ)」を公表し、生活習慣病等の予防・重症化予防、健康づくりの推進、がん検診等の充実による早期発見・早期治療、多剤重複投薬対策や重複検査対策などを進めることで医療費適正化の効果も得られるとされていること
- ・日本維新の会として、令和7年2月20日に「社会保険料を下げる改革案(たたき台)」を公表し、国民医療費の総額を、年間で最低4兆円削減することによって、現役世代一人当たりの社会保険料負担を年間6万円引き下げるとされていること
を念頭に置く。
-
III
働き控えの解消
社会保険に係るいわゆる年収の壁による働き控えの解消に向けて、「年収130万円の壁」について、手取りの減による働き控えの解消を図るため、被用者保険への移行を促し、壁を意識せず働くことができるよう、賃上げや就業時間の延長等を通じて労働者の収入を増加させる事業主を支援する措置を令和7年度中から実施する。従来、「年収106万円の壁」への対応として実施しているキャリアァップ助成金による措置を拡充することとし、その際、中小・小規模事業者への支援強化や使い勝手の更なる向上等を行う。この措置は、労働保険特別会計において臨時に行う時限的措置とし、第三号被保険者制度のあり方を含めた「年収130万円の壁」に関する制度的な対応のあり方について更に検討を進める。
-
IV
教育無償化に関する論点等
-
1.
いわゆる高校無償化について、義務教育との関係、公立高校(農業高校、水産高校、工業高校、商業高校等の専門高校を含む)などへの支援の拡充を含む教育の質の確保、多様な人材育成の実現、収入要件の撤廃を前提とした支援対象者の範囲の考え方、私立加算金額の水準の考え方(令和8年度は45.7万円)、支給方法の考え方(代理受領か直接支給か、DX化による効率化の推進)、高校間での単位互換、国と地方の関係、公立と私立の関係、現場レベルの負担といった論点について、十分な検討を行う。
-
2.
いわゆる給食無償化については、地方自治体に対して、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した対応を促すとともに、「学校給食法」との関係、児童生徒間の公平性、支援対象者の範囲の考え方、地産地消の推進を含む給食の質の向上、国と地方の関係、効果検証といった論点について、十分な検討を行う。
-
3.
0~2歳を含む幼児教育・保育の支援については、更なる負担軽減・支援の拡充について、論点を整理した上で十分な検討を行い、その結果に基づき、成案を得る。
-
4.
高等教育の支援については、更なる負担軽減・支援の拡充について、論点を整理した上で十分な検討を行い、その結果に基づき、成案を得ていく。
-
5.
上記の各施策の実現に当たっては、政府全体で徹底した行財政改革を行うことなどにより安定財源を確保する。
-
-
V
上記Ⅰ~Ⅳを前提に、令和7年度予算及び令和7年度税制改正法について、所要の修正を行った上で、年度内の早期に成立させる。令和8年度以降の措置については「骨太方針2025」に記載し、令和8年度以降の予算に反映させる。記載のない共通理解について、国会における政府答弁によって可能な限り確認を行う。
合意後も引き続き、自由民主党、公明党、日本維新の会の3党の枠組みで、合意事項の実現に責任と誠意をもって取り組む。
以上
自由民主党、公明党、日本維新の会
合意
自由民主党、公明党、日本維新の会は、持続可能な社会保障制度のための改革を実行し、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を実現するため、以下の通り合意する。

-
1.
社会保障改革による国民負担の軽減を実現するための3党の協議体の成果の一環として、次の2点を実現する。
-
(1)
病床再編の拡大
人口減少等により不要となると推定される、約11万床(※1)の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、2年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図ることとし、その旨を骨太の方針に明記する。当該削減が実現した際には、「一定の合理性のある試算」(※2)に基づけば、約1兆円の医療費削減効果と計算されるなど、一定規模の入院医療費の削減効果が期待できる。その上で、感染症等に対応する病床は確実に確保しつつ、削減される病床の区分や病床の稼働状況、代替する在宅・外来医療等の増加等を考慮した上で、精査を行う。
- (※1)一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数約5万6千床並びに精神病床の基準病床数を超える病床数約5万3千床を合算した病床数(厚生労働省調べ)。
- (※2)別紙参照
-
(2)
医療DXの加速化
現時点の電子カルテ普及率が約50%であることに鑑み、普及率約100%を達成するべく、5年以内の実質的な実現を見据え電子カルテを含む医療機関の電子化を実現する。また、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子カルテを通じた医療情報の社会保険診療報酬支払基金に対する電磁的提供を実現する。
-
-
2.
上記を踏まえ、政府提出の「医療法等の一部を改正する法律案」に対し、上記の病床再編の拡大及び医療DXの加速化について、本則及び附則において所要の修正を行った上で、本年の国会における成立を図る。
-
3.
介護・障害福祉従事者の処遇改善が喫緊の課題であることに鑑み、「介護・障害福祉従事者処遇改善法案」と比較してより安定的・効果的かつ機動的な対応の必要性を認識した上で、政府が過去に実施した措置を念頭に、報酬改定(例:平成29年度臨時改定の処遇改善加算拡充(1万円相当)等)や予算措置(例:平成21年度補正予算による処遇改善の交付金措置(1.5万円相当)、令和3年度補正予算による処遇改善の交付金措置(9千円相当)等)を組み合わせて、機動的に必要な対応を行う。
-
4.
上記1 ~ 3に加えて、引き続き3党の協議体において、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を実現するため、社会保障改革に関する真摯な協議を継続する。その際に協議する施策については、『自由民主党、公明党、日本維新の会合意』(令和7年2月25日)に基づき、令和7年末までの予算編成過程(診療報酬改定を含む)で論点の十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、令和8年度から実行に移す。また、令和8年度以降の措置については「骨太方針2025」に記載し、令和8年度以降の予算に反映させる。なお、本合意について、3党は、政府提出の「医療法等の一部を改正する法律案」の本年における成立に限定して責任をもって努力することとする。
以上
【別紙】医療需要等の変化を踏まえた一定の合理性のある試算
(厚生労働省の調査に基づく日本維新の会の試算)
1. 必要予算額の試算
-
削減し得る病床の総計(厚生労働省調べ)
- ► 一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数:約5万6千床
- ► 精神病床の基準病床数を超える病床数:約5万3千床
- ► 合計:約11万床
-
病床の効率化・適正化を加速化する場合
- ► 約11万床の不要病床について、2年間で加速化して効率化する場合、5.5万床/年の適正化が必要。
-
現在の政府事業をベースに、当該事業を拡大した場合の必要資金
- A.病床の削減:一般病院等に対して、1床あたり約410万円(4,104千円)の給付金を支給(令和6年度補正予算事業を参照)
- B.病棟の機能転換:以下を行う病院に対して、病棟あたり2千万円の給付金の支給と仮定(対象は約250病棟と推計)
- ■ 7: 1→地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟へ転換
- ■ 10: 1→地域包括ケア病棟への転換
- C.医療機関の業態変更:以下を行う病院に対して、1病院あたり2千万円の給付金の支給と仮定(対象は約250病院と推計)
- ■ 在宅療養支援病院又は後方支援病院の取得
-
財政試算(必要予算額)
- A. 5.5万床/年x410万円=2,255億円/年
- B. 250病棟x2千万円=50億円/年
- C. 250病院x2千万円=50億円/年
A+B+C = 2,355億円/年 ≒ 約2,400億円/年(4,800億円/2年)
2.効率化・適正化総額の試算
-
病床の削減(一般病院十ケアミックス病院)
- ► 一般病院1床あたり医業収益:22,932千円/床年≒2,300万円/床年
- ► ケアミックス病院1床あたり医業収益:14,255千円/床年≒1,400万円/床年
- ► (2,300+1,400)万円/床年÷2x(5.6万床÷2)=5,180億円/年
-
病床の削減(精神科病院)
- ► 精神病院1床あたり医業収益:7,049千円/床年≒700万円/床年
- ► 700万円/床年x(5.3万床:2)=1,855億円/年
-
病床の削減(全体)
- ► 不要となる病床の総計11万床の全てを完遂する場合
5,180億円/年+1,855億円/年=7,035億円/年≒7,000億円/年≒1.4兆円/2年
- ► 不要となる病床の総計11万床の全てを完遂する場合
-
財政試算(適正化効果額)
- ► 必要予算額:約2,400億円/年
- ► 削減総額 :約7,000億円/年
- ► 適正化効果額(最大):7,000-2,400 = 4,600億円/年
≒5千億円/年(約1兆円/2年)
以上
自由民主党、公明党、日本維新の会
合意
自由民主党、公明党、日本維新の会は、持続可能な社会保障制度のための改革を実行し、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を実現するための3党の協議体における議論の成果を「骨太方針2025」に反映するため、先般、6月6日に実務者問で先行的に合意に達した事項を含め、以下の通り合意する。
自由民主党、公明党は、本合意内容の趣旨を「骨太方針2025」に反映する。その上で3党は、引き続き、本協議体における社会保障改革に関する真摯な協議を継続する。
【OTC類似薬の保険給付のあり方の見直し】
類似のOTC医薬品が存在する医療用医薬品(OTC類似薬)の保険給付のあり方の見直しについては、医療の質やアクセスの確保、患者の利便性に配慮しつつ、医療保険制度の持続可能性確保を目指すことを基本とし、令和7年末までの予算編成過程で十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、令和8年度から実行する。
その際、医療機関における必要な受診を確保し、こどもや慢性疾患を抱えている方、低所得の方の患者負担などに配慮しつつ、成分や用量がOTC医薬品と同等のOTC類似薬をはじめとするOTC類似薬一般について保険給付のあり方の見直しの早期実施を目指す。その中で、個別品目に関する対応についても、これまでのビタミン剤やうがい薬、湿布薬に関する対応を踏まえ、適正使用の取組を検討する。
あわせて、セルフメディケーション推進の観点から、スイッチOTC化に係る政府目標(※)の達成に向けた取組を着実に進めるとともに、夏以降、当初の医師の診断や処方を前提にしつつ、症状の安定している患者にかかる定期的な医薬品・検査薬のスイッチOTC化に向けて、制度面での必要な対応を含め、更なる実効的な方策を検討する。
(※)令和5年末時点で海外2か国以上でスイッチOTC化されている医薬品のうち、本邦でスイッチOTC化されていない医薬品(約60成分)を令和8年末までにOTC化する。
【新たな地域医療構想に向けた病床削減】
人口減少等により不要となると推定される、約11万床(※1)の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情を踏まえた調査を行った上で、2年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図る。当該削減が実現した際には、「一定の合理性のある試算J(※2)に基づけば、約1兆円の医療脅削減効果と計算されるなど、一定規模の入院医療贄の削減効果が期待できる。その上で、感染症等に対応する病床は確実に確保しつつ、削減される病床の区分や病床の稼働状況、代替する在宅外来医療等の増加等を考慮した上で、精査を行う。
- (※1)一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数約5万6千床並びに精神病床の基準病床数を超える病床数約5万3千床を合算した病床数(厚生労働省調べ)。
- (※2)別紙参照
【医療DXを通じた効率的で質の高い医療の実現】
現時点の電子カルテ普及率が約50%てあることに鑑み、普及率約100%を達成するべく、5年以内の実質的な実現を見据え電子カルテを含む医療機関の電子化を実現する。また、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子カルテを通じた医療情報の社会保険診療報酬支払基金に対する電磁的提供を実現する。
【地域フォーミュラリの全国展開】
有効性や安全性に加えて、経済性を踏まえて作成される「地域フォーミュラリ」(「医薬品のリスト・使用指針」)の導入について、現状、極めて限定的となっている状況を踏まえ、その普及に向けて、後発医薬品の更なる使用促進や患者の自己負担抑制等の観点から、普及推進策を検討し、各地域において地域フォーミュラリが策定されるよう取組を推進する。
【現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しによる応能負担の徹底】
医療・介護保険における負担への金融所得の反映の在り方について、現役世代に負担が偏りがちな構造の見直しの観点から、税制における確定申告の有無により負担等が変わる不公平な取扱いを是正する必要がある。保険者が金融機関等からの情報を基に確定申告されていない金融所得を負担の公平性の観点から反映させる方法などが考えられるが、税制における金融所得に係る法定調書の現状も踏まえつつ、マイナンバーの記載や情報提出のオンライン化等の課題、負担等の公平性、関係者の事務負担等に留意しながら、どのように金融所得の情報を反映させるかを含め、具体的な制度設計を進める。年齢に関わらず負担能力に応じた負担を目指す観点から、現役世代から後期高齢者への支援金負担の軽減に配慮する。
【生活習慣病の重症化予防とデータヘルスの推進】
がんを含む生活習慣病の重症化予防の推進は、患者のQOLの向上や健康寿命の延伸のみならず、医療費の抑制効果も期待できる。
このため、糖尿病患者に対する重症化予防による糖尿病に起因する下肢切断の回避や、ヘリコバクター・ピロリの除菌治療による胃がんの発症予防といった疾病予防が医療費に与える影響の分析を進めるとともに、糖尿病性腎症の重症化予防等におけるデータヘルスの取組の推進など、生活習慣病の重症化予防、リスクに応じたがん検診等の充実による早期発見・早期治療に取り組んでいく。併せて、医療DXの推進による医療情報等の共有の取組を進めつつ、データヘルスの更なる強化に取り組む。
以上

【別紙】医療需要等の変化を踏まえた一定の合理性のある試算
(厚生労働省の調査に基づく日本維新の会の試算)
1. 必要予算額の試算
-
削減し得る病床の総計(厚生労働省調べ)
- ► 一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数:約5万6千床
- ► 精神病床の基準病床数を超える病床数:約5万3千床
- ► 合計:約11万床
-
病床の効率化・適正化を加速化する場合
- ► 約11万床の不要病床について、2年間で加速化して効率化する場合、5.5万床/年の適正化が必要。
-
現在の政府事業をベースに、当該事業を拡大した場合の必要資金
- A. 病床の削減:一般病院等に対して、1床あたり約410万円(4,104千円)の給付金を支給(令和6年度補正予算事業を参照)
- B. 病棟の機能転換:以下を行う病院に対して、病棟あたり2千万円の給付金を支給(対象:約250病棟と推計)
- ■ 7:1病棟 → 地域包括医療病棟または地域包括ケア病棟へ転換
- ■ 10:1病棟 → 地域包括ケア病棟へ転換
- C. 医療機関の業態変更:以下を行う病院に対して、1病院あたり2千万円の給付金を支給(対象:約250病院と推計)
- ■ 在宅療養支援病院または後方支援病院の取得
-
財政試算(必要予算額)
- A. 5.5万床/年x410万円=2,255億円/年
- B. 250病棟x2千万円=50億円/年
- C. 250病院x2千万円=50億円/年
A+B+C = 2,355億円/年 ≒ 約2,400億円/年(4,800億円/2年)
2. 効率化・適正化総額の試算
-
病床の削減(一般病院+ケアミックス病院)
- ► 一般病院1床あたり医業収益:22,932千円/床年≒2,300万円/床年
- ► ケアミックス病院1床あたり医業収益:14,255千円/床年≒1,400万円/床年
- ► (2,300+ 1,400)万円/床年÷2x(5.6万床÷2) =5,180億円/年
-
病床の削減(精神科病院)
- ► 精神病院1床あたり医業収益:7,049千円/床年≒700万円/床年
- ► 700万円/床年x(5.3万床÷2) = 1,855億円/年
-
病床の削減(全体)
- ► 不要となる病床の総計11万床の全てを完遂する場合
5,180億円/年+1,855億円/年=7,035億円/年≒7,000億円/年≒1.4兆円/2年
- ► 不要となる病床の総計11万床の全てを完遂する場合
-
財政試算(適正化効果額)
- ► 必要予算額:約2,400億円/年
- ► 削減総額 :約7,000億円/年
- ► 適正化効果額(最大):7,000-2,400 = 4,600億円/年
≒5千億円/年(約1兆円/2年)
以上
附属書
「骨太方針 2025」に反映する政策に加えて、引き続き3党の協議体において、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を実現するため、社会保障改革に関する真摯な協議を継続する。その際に協議する施策については、『自由民主党、公明党、日本維新の会 合意』(令和7年2月25日)に基づき、令和7年末までの予算編成過程(診療報酬改定を含む)で論点の十分な検討を行い、早期に実現が可能なものについて、令和8年度から実行に移す。
このような観点から、日本維新の会は、現役世代の社会保険料の引き下げを実現するために、以下の改革項目について提起し、3党の協議体において議論を行うことを提案する。
-
1.
国民皆保険制度を守るための公的保険の在り方及び民間保険の活用の在り方
-
2.
医療の費用対効果確認の徹底
-
3.
低価値医療の保険適用の在り方の見直し
-
4.
真の応能負担の実現(窓口負担に関する世代間の公平の確保)
-
5.
インフレ下における医療提供体制の在り方を踏まえた改革
-
6.
中央社会保険医療協議会の在り方の見直し
-
7.
終末期医療の在り方
-
8.
病院の電子カルテ等のシステムの標準化の加速化
-
9.
人材紹介手数料の負担軽減、ハローワークの利便性改善
-
10.
マイナポータル期間連携API等を通じたデジタル予防医療の推進
-
11.
プログラム医療機器の普及に係る市場環境の整備促進
-
12.
介護テクノロジーとノーリフトケアの推進等を通じた介護現場の負担軽減
-
13.
後発医薬品へのアクセス向上、バイオシミラーの使用促進
-
14.
健康寿命の延伸に資する歯科検診の普及
-
15.
多剤・重複投与(ポリファーマシー)の防止による高齢者の安全性確保
-
16.
保険者機能の強化
-
17.
オンライン診療の普及促進
-
18.
感冒用症状の検査及び予防接種に関するアクセス向上
-
19.
特定健診に関する効果が望まれる年齢層への集中投資
-
20.
複雑化した調剤報酬体系の簡素化
-
21.
医療機関の外来診療における診療報酬体系の在り方の改革 等
以上