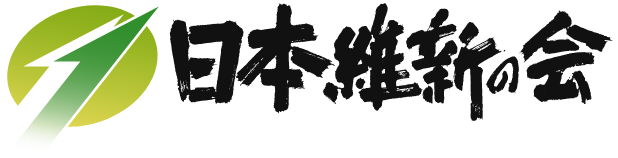日本維新の会は、地方から国の形を変えることを
目的に設立された地方分権型政党であり、
東京の本部を頂点とするピラミッド形の既存政党と
は全く異なる組織形態を持っています。
日本維新の会は、国は外交防衛やマクロ経済政策など
国でしか行えない政策に専念するとともに、
住民生活に関わる多くの部分については
地方自治体に権限と財源を移譲し、
地域のことは地域で決める(二アイズベター)体制へと
転換するという考え方のもと、
各地域がその地域特性に応じた
自律的な発展を実現するための指針
「地域版マニフェスト」を策定しています。